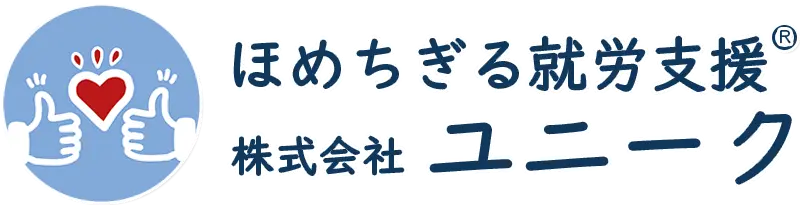就労継続支援A型事業所(以下、A型作業所)での就職を考えている場合、給料はいくらになるのか、経済的な面が気になる方も多いのではないでしょうか。
A型作業所は雇用契約を結んで働く場所であり、安定した収入が得られることが魅力です。
しかし、具体的な給料の目安や、そこから引かれるお金、さらには利用料の有無など、疑問に思う点も多いでしょう。
この記事では、A型作業所の給料について、全国の平均相場や手取り額のシミュレーション、生活を支えるための各種制度を紹介します。
A型作業所の給料はどれくらい?
A型作業所の給料は、雇用契約に基づいて支払われるため、国が定める最低賃金法が適用されます。
そのため、地域や勤務時間によって変動はありますが、安定した収入を得られることが特徴です。
最初に、A型作業所の給料の目安や、B型事業所との違いについて詳しく見ていきましょう。
全国の平均月収と時給の目安
厚生労働省の調査によると、A型作業所の全国平均月収は、およそ8万円程度が目安です。
しかし、この金額はあくまでも平均であり、実際の給料は事業所の所在地、仕事内容、個人の勤務時間によって大きく変わることを理解しておきましょう。
都市部では最低賃金が高い傾向にあるため、地方よりも月収が高くなる傾向があります。
また、時給制で働くことが多いため、勤務時間が長いほど、必然的に月収も高くなります。
時給は最低賃金以上!働き方で変わる収入の目安
A型作業所の給料は、最低賃金以上であることが法律で定められています。
一般企業と同じく、雇用契約に基づく労働者として扱われるためです。
例えば、地域の最低賃金が時給1,000円だった場合、1日6時間、週5日勤務で週給3万円、月給では約12万円になります。
さらに、残業や休日出勤が発生した場合は、その分が上乗せされます。
このように、A型作業所では、自身の働き方次第で収入をある程度コントロールできる点が大きな魅力です。
B型事業所との収入の違い
A型作業所とB型事業所の最も大きな違いは、収入の形態にあります。
A型作業所が「給料」であるのに対し、B型事業所は「工賃」です。
B型事業所の工賃は最低賃金法の適用外であり、全国平均月額は23,000円程度と、A型作業所に比べて低くなります。
これは、B型事業所が雇用契約を結ばない、体調やペースを優先した働き方を目的としているためです。
経済的な自立を目指すのであればA型作業所、無理なく自分のペースで社会参加したいのであればB型事業所と、自身の目的によって選ぶべき場所が変わってきます。
手取りはいくらになる?利用料や保険料のこと
A型作業所は、雇用契約を結ぶため、給料から税金や社会保険料が引かれます。
また、「利用料」というものがかかるのかも気になる方が多いのではないでしょうか。
ここでは、給料から引かれるものや、実際の手取り額について解説します。
給料から引かれるもの(税金・保険料)
A型作業所でも、給料から引かれる項目は一般企業と同じです。
所得税:給料の金額に応じて課税されます。
住民税:前年の所得に応じて課税されます。
社会保険料:健康保険、厚生年金保険、雇用保険料が引かれます。
なお、所得が一定額以下の場合は、所得税や住民税が非課税になることもあり、社会保険への加入は雇用条件によって異なります。
週の労働時間や日数が、一定の基準を満たしている場合に加入対象です。
これにより、将来の年金受給資格や医療費の自己負担額が軽減されるなどのメリットがあります。
A型利用料ってかかるの?
A型作業所の利用料については、原則として無料です。
これは、障害福祉サービスに位置づけられており、国や自治体がその費用を負担しているためです。
ただし、前年度の世帯所得によっては、ごく一部の方が利用料を負担するケースもあります。
しかし、ほとんどの利用者の方は利用料を支払うことなくサービスを受けられるため、給料から利用料が天引きされる心配はありません。
実際の手取りシミュレーション
例えば、最低賃金が時給1,000円の地域で、週5日、1日6時間勤務した場合を想定します。
月収:1,000円 × 6時間 × 20日 = 120,000円
引かれるお金(概算)
所得税:約2,000円
住民税:約3,000円
社会保険料:約15,000円
手取り額:120,000円 – (2,000円 + 3,000円 + 15,000円) = 約100,000円
これはあくまでも一例であり、個人の状況や勤務時間、地域によって変動します。
しかし、このように手取り額を事前に把握しておくことで、生活設計が立てやすくなるでしょう。
生活費を助けてくれる制度もある!
A型作業所の給料だけでは、生活費が十分に賄えないのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。
しかし、A型作業所で働きながら、生活をサポートしてくれる様々な公的な制度があります。
これらの制度を上手に活用することで、経済的な不安を軽減し、より安定した生活を送ることが可能になります。
障害年金との併用が可能
A型作業所で働きながらでも、障害年金を受給することは可能です。
障害年金は、障害を抱える方が生活を安定させるための大切な制度であり、給料とは別に支給されます。
この制度を併用することで、収入を大幅に増やせます。
障害年金の受給資格があるかどうかは、個人の障害の状態や加入している年金制度によって異なるため、年金事務所や自治体の窓口に相談してみましょう。
生活保護や自治体の支援制度
A型作業所の給料が生活費に満たない場合、生活保護との併用も可能です。
生活保護制度は最低限度の生活を保障するための制度であり、A型作業所の給料を収入として申告したうえで不足分が支給されます。
また、各自治体では、障害を持つ方の就労や生活を支援するための独自の制度を設けている場合があります。
例えば、通勤費の補助や就労に必要な物品購入費の補助などがあるため、住んでいる地域の福祉課に問い合わせてみましょう。
将来のステップアップで収入アップを目指す
A型作業所での経験は、将来の収入アップにつながる大切なステップです。
働き続けることでスキルや経験が身につき、事業所内での昇給や、より高い給料を得られる事業所への転職、一般企業への就職を目指すことも可能です。
A型作業所は、「働く場所」というだけではなくキャリアアップのための訓練の場でもあります。
給料を安定させながら、将来の選択肢を広げるための準備ができるのです。
まとめ
A型作業所は、最低賃金以上の安定した収入を得ながら、自分のペースで働くことができます。
さらに、障害年金や生活保護などの公的制度と併用することで、経済的な基盤をしっかりと築くことも可能です。
A型作業所の給料や、様々な支援制度を理解することで、不安は大きく軽減されます。
経済面が不安な方は、自身の希望する働き方や地域の最低賃金を考慮して、事前に事業所の給料体系を確認しましょう。