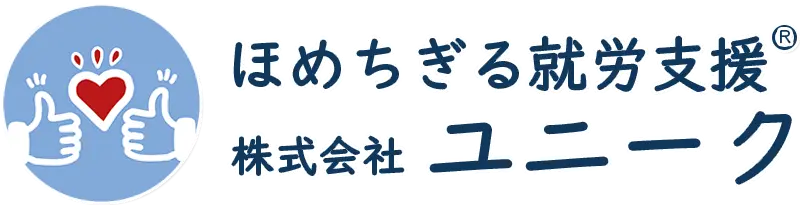「就労支援」という言葉を聞いたことはあるものの、具体的にどのような場所なのか、そして「A型」と「B型」の違いがよくわからないという方は少なくありません。
特に、これから就職や社会復帰を目指したいと考えている方にとって、自分に合った事業所を見つけることは大切です。
本記事では、就労支援のA型とB型の違いについて、それぞれの特徴、仕事内容、給料などを解説します。
A型事業所とB型事業所って何が違うの?はじめてでもわかる基本ガイド
就労継続支援には、A型事業所とB型事業所の2つの種類があります。
これらの違いを理解することは、自分にとって最適な支援を選ぶために重要です。
最初に、それぞれの基本的な特徴や、どのような方が利用できるのかについて解説します。
A型事業所は「雇用契約アリ」のお仕事スタイル
就労継続支援A型事業所は、利用者と事業所が雇用契約を結び、働く場所です。
この雇用契約があるため、利用者は最低賃金法が適用され、安定した収入を得られます。
A型事業所は、一般企業での就労は難しいものの、雇用契約を結んで働くことができる方が対象です。
仕事内容も多岐にわたり、事務作業や軽作業、清掃、データ入力など、事業所によって様々です。
一般企業への就職を目指すためのスキルアップの場でもあり、働くことへの自信を取り戻すためのステップとして活用する方もいます。
B型事業所は「工賃制」で自分のペースを大切にできる
就労継続支援B型事業所は、雇用契約を結ばずに、自分の体調やペースに合わせて働ける場所です。
そのため、働くことで得るものは「給料」ではなく、「工賃」と呼ばれます。
B型事業所の大きな特徴は、働く時間や日数を自由に調整できることです。
体調の波がある方や、まずは少しずつ社会に参加したいと考えている方にとって、無理なく自分のペースで活動できる最適な環境といえるでしょう。
仕事内容も、手作業での簡単な組み立てや内職、農作業など、比較的負担の少ないものが多く、それぞれの能力や特性に合わせて取り組めます。
こんな人が対象!A型・B型それぞれの利用条件
就労継続支援の対象者は、原則として、障がいや病気と付き合いながら働きたい人が対象です。
しかし、A型とB型では、利用できる条件が若干異なります。
A型事業所は、主に一般企業での就労が困難であり、かつ雇用契約を結んで働くことが可能と判断された方が対象です。
年齢の上限が設けられている場合もあります。
一方で、B型事業所は、A型事業所や一般企業での就労が難しい方または一定の年齢に達していて就労経験が少ない方などが対象です。
医師の診断や自治体の判断によって利用が認められることが一般的です。
利用者目線で見る!A型・B型それぞれのメリット・デメリット
A型事業所のメリットは、雇用契約に基づく安定した収入が得られることです。
社会保険に加入できる場合もあり、経済的な自立を目指しやすい点がメリットです。
また、働く中でビジネスマナーやスキルを習得でき、一般就労への移行もしやすくなります。
しかし、雇用契約があるため、決められた勤務時間やノルマがあり、体調によっては負担に感じてしまうこともあるでしょう。
一方、B型事業所は、自分のペースで無理なく働けることがメリットです。
体調を最優先に考えられるため、ストレスを最小限に抑えながら社会参加ができます。
ただし、工賃が低く設定されていることが多く、経済的な自立は難しいケースもある点に注意が必要です。
A型・B型それぞれの仕事内容・給料・時間の違いをやさしく比較!
就労継続支援事業所を選ぶうえで、具体的な仕事内容や、収入、勤務時間は重要なポイントです。
ここでは、A型事業所とB型事業所のそれぞれの具体的な違いを解説します。
どのような仕事をするの?A型・B型それぞれの作業例
A型事業所の仕事内容は、一般企業の業務に近いものが多く、より実践的なスキルを身につけられます。
例えば、パソコンを使ったデータ入力や書類作成、電話応対、ウェブサイトの運営サポートなど、事務系の作業があります。
その他にも、食品の製造・加工、パンの販売、清掃、農作物の栽培など、様々です。
B型事業所の仕事は、比較的単純な軽作業が多いです。
作業では部品の組み立てや、商品の袋詰め、封入作業、手工芸品の制作、清掃、農作物の収穫などが挙げられます。
お給料や工賃の目安はこれくらい
A型事業所では、雇用契約に基づいて都道府県が定める最低賃金以上の給料が支払われます。
そのため、安定した収入を得ることが可能です。
具体的な金額は勤務時間や地域によって異なりますが、月収約8万円が目安です。
B型事業所で支払われるのは「工賃」であり、最低賃金法の適用はありません。
工賃は、作業量や事業所の売上によって変動するため、金額はA型事業所よりも低くなる傾向にあります。
全国平均では月額2万円台が目安とされていますが、これも事業所や個人の作業実績によって大きく変わります。
勤務時間や利用期間はどう違う?
A型事業所の勤務時間は雇用契約に基づいて決定されるため、1日数時間からフルタイムまで、事業所によって様々です。
一般企業と同じように、週に何日か働くというスタイルになります。
利用期間に明確な期限は設けられていませんが、一般就労を目指すためのステップとして利用する方が多いです。
一方、B型事業所は、働く時間や日数を個人の体調に合わせて自由に設定できます。
例えば、週に1回、1日2時間だけといった利用も可能です。
利用期間に制限はなく、長く利用を続けることができるため、自分のペースで社会参加したい方に適しています。
事業所利用までの流れと必要な手続き
就労支援事業所の利用を考えている方が、実際に利用を開始するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。
ここでは、スムーズに手続きを進めるための流れと、必要な書類について詳しく解説します。
まずは見学や体験からスタート
就労支援事業所を利用する前に、まずは見学や体験利用がおすすめです。
実際に足を運んで、事業所の雰囲気や仕事内容、スタッフとの相性を確かめましょう。
多くの事業所では、見学や体験利用を随時受け付けています。
見学や体験の段階ではまだ正式な手続きは必要ないため、複数の事業所を比較検討してみるのも良いでしょう。
申し込みから「受給者証」取得までのステップ
実際に利用したい事業所が決まったら、正式な申し込み手続きに入ります。
この手続きは、市区町村の役所の窓口で行います。
最初に、市区町村の障がい福祉課などの窓口に相談し、就労継続支援の利用を希望する旨を伝えましょう。
窓口で必要書類を受け取り、申請書に記入します。
市区町村の担当者による面談が行われ、審査が通ると、「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。
これは就労継続支援事業所を利用するための証明書であり、受給者証が手元に届いたら、事業所との契約に進みます。
利用開始後のサポート体制
就労継続支援事業所の利用が始まると、事業所のスタッフが一人ひとりの状況に合わせて、様々なサポートを提供してくれます。
仕事に関することや、日常生活での悩み相談、体調管理のアドバイスなど、利用者の方が安心して活動できるような支援体制が整っています。
一般就労への移行を目指す方には、履歴書の作成や面接の練習など、より具体的な就職活動のサポートも受けることが可能です。
まとめ
就労継続支援A型とB型は、どちらも働くことを通じて社会参加を目指すための大切な場所です。
雇用契約を結んで働くA型は、安定した収入を得ながら一般就労を目指す方に向いています。
一方で、雇用契約を結ばず、自分のペースで無理なく働けるB型は、体調を優先しながら社会とつながりたいと考える方に最適です。
自身の障がいの状況、体調、どのような働き方をしたいかという希望に合わせて、適した事業所を選択しましょう。